日本初の障害者の表現を紹介する民設美術館がつなぐ支援 ーとちぎアートサポートセンターTAM(栃木県)
障害のある人の芸術活動を中心とする美術館が母体の支援センターとは?

とちぎアートサポートセンターTAM(以下、TAM)は、認定NPO法人もうひとつの美術館の運営するもうひとつの美術館内に2017年に設置された障害者芸術文化活動支援センター(以下、支援センター)だ。もうひとつの美術館は、
今回は、もうひとつの美術館 館長の梶原紀子さんと、支援センター業務を担当するスタッフの五味渕仁美さんに、20年以上運営してきた美術館としての蓄積が、支援センターとしての活動にどんな影響があるのかについて取材してきた。
里山の木造元小学校校舎を美術館にしたわけ
もうひとつの美術館の設立者で館長の梶原さんは、陶芸家を目指したり、建築を学んだりしていたそうだ。結婚して二人の子供の子育てをしていた時期に、家族にとってより良い環境を求め、1998年に家族4人で東京から那珂川町に移住。ちょうどその頃、障害のあるアーティストたちの展覧会「このアートで元気になる エイブル・アート’99」と、知的障害を抱える7人のアーティストの創作活動を追ったドキュメンタリー映画「まひるのほし」に触れ、それぞれから強い衝撃を受けた。梶原さんの敬愛する陶芸家八木一夫さんが障害者の創作活動のサポートボランティアをしていたことにも感化され、自身も障害者の創作の環境を整えたり、支えたり、既成の枠にとらわれない障害者の表現を作品として認め、伝える人になりたいと思いはじめたのだそうだ。

元小学校校舎を活用した「もうひとつの美術館」

2024年11月まで開催されていた「これは文字?記号?それとも暗号?」展示風景
梶原 また時を同じくして2001年に小口小学校が廃校になり、この素敵な校舎の良さを活かしながら何かできないかと考えました。当時は障害者のアート活動について、まだ知られていませんでしたし、美術館もなかったんです。世の中にひとつぐらいあっても良いと思って、障害者の芸術活動を支援する場所にしようと思い立ちました。
梶原 予算が少なくて、手弁当でやっていることも多く、スタッフ6名では手が足りませんし、美術館運営は本当に大変なんです。それでも、全国の福祉施設を回って、アーティストたちと出会い、企画を考え、作品やショップに並べる品を集めてきます。障害者のアートに対する認識を変えていきたいし、訪れる方にもより良いものを見てほしいから、展示する作品もショップで扱う品も、こだわりを持って選ぼうと意識しています。
厚労省の支援事業がスタートした際には、
ちょっとした相談の多い美術館
もうひとつの美術館は、最寄りのバス停から徒歩25分と、公共交通機関でのアクセスは決して良くない。だがその分、アットホームな魅力がある。訪れた人は展覧会をみた後、ショップで買い物を楽しみ、カフェでお茶を飲んで長居をするのだろう。
五味渕 私は展覧会の受付をしたり、ミュージアムショップにいたりしています。普通、美術館ではスタッフとお客様とが気軽に話をする機会はあまりありませんが、私や当館スタッフはよくお客様と話します。鑑賞後に感想を聞いている中で、ちょっとした悩みを相談してくださるお客様も多いですね。これは支援センターの相談支援業務なのでは、と、ふと後になって気がつくこともあるぐらいで(笑)。
ちょっとしたお喋りの延長から「絵を描くのが好きみたいなのだけど」「どこかで展示をしてみたい」といった相談事が交わされ、「それならここを調べてみては」と、ごく自然な形で相談支援が成立していることもあるそうだ。地域の中でも障害者の芸術活動を支援するアイコニックな存在だからこそ、「この美術館のスタッフなら、詳しいだろうし、何か教えてくれるかも」と、思われるような存在感と親しみやすさを示せているのである。
梶原 支援センターを開設する以前からそうなんです。今はちゃんと相談支援業務として、窓口があり、電話やメールで相談を受け付けていますが、それでもやっぱり、こうした美術館業務の延長で交わされる話の中にある相談事は、相変わらずありますね。
訪れる人に頼られて、自然に相談が生まれる状態を生み出せているのは、美術館としても、支援センターとしても、市民の広場として機能している点で、理想的な姿といえる。
支援センターとしての事業は、こうした相談業務の他、公募のViewing展と、アートに関する研修とネットワーキングを目的としたTAM会議に力を注いでいる。
眺めが良い県庁の上階ではじまった公募「Viewing」展

「Viewing展(2016年)」の展示風景
美術館の冬季休業期間に年に1度開催されている展覧会がViewing展だ。2016年にスタートし、今年で10度目の開催となる。当初は県庁の15階展望ロビーで開催されており、現在は冬季休業期間中の美術館や栃木県総合文化センターを会場に開催をしている。公募の対象地域は栃木県だが、以前は支援センターが設置されていなかった群馬や茨城からも引き続き応募がある。応募作品には専門家による選考が実施され、今年は応募総数407点から258点が選ばれた。

「Viewing展2025」 選考会の様子
梶原 作家をできるだけ理解したいので、複数点を出品してもらうようにしています。選考といっても、最終的には好みになるんですよね。それでいいと思っています。大切なのはその人が集中して作っているかと自発的な創作かどうか。自発性については作品を見ればすぐにわかりますね。
告知にも力を入れ、チラシや県の広報媒体(メーリングリスト、LINE、広報誌)やローカルラジオなど、活用できるものは全て活用している。
五味渕 県の担当者がラジオに出演して展覧会の告知をしてくれたこともありました。車社会なので、通勤時などは皆さん良くラジオを聞いていて、とても効果があります。ただやはり、広報には常に課題感があって、事後に開催を知って、『参加したかった』といってくださる方もいて。もっと工夫して広げていきたいです。
新しい作家と出会う広報活動も欠かすことができない一方で、参加してくれた作家とのつながりを大切にしているのが特徴だ。出展作家のメーリングリストを作り、様々なお知らせを送っている。情報を共有することで、出展作家の横のつながりをつくる工夫である。また、このViewing展は、TAM事業の研修の場となって活用されている。
県内に活動を広げる人材を育成
TAM会議は研修とネットワーキングの場として開催されており、人材育成事業としての意味合いが強い。年に4〜5回の会議には、その年のViewing展のレイアウトを考える研修と、同じくViewing展の設営と運営を考える研修が含まれている。実際に展覧会を企画・運営している美術館で、展覧会づくりを学ぶことができる、貴重な機会である。

TAM会議の様子

「Viewing展2023」設営風景
五味渕 アート的な視点と、福祉的な視点では捉え方が違いますが、言葉にして伝えるのはなかなかの難しさがあります。そうした視点を、実際に一緒に活動をしていく中で、自然と学び取っていただけている実感があります。『自分の事業所での活動にTAMで学んだことをフル活用しています!』と言ってくださった参加者もいて、とても嬉しかったですね。
TAM会議参加者の属性は福祉事業所のスタッフ、実際に作品を制作している作家、こうした活動を手伝いたいと考えている人、これから何か始めたい人などと様々。毎年参加をしている人もいれば、初めての人も。
五味渕 参加者同士で情報交換をしてもらったり、『これは表現?』をテーマに話し合っていただく機会も作っていて、多くの活動や考え方に出会える場所です。年度の途中からの参加も歓迎で、まだ何をしていいかわからないという人でも、情報交換から初めて、ゆるりと参加していただけたらいいなと思っています。
梶原さんや五味渕さんは、あくまでも謙虚で飾らない人柄なのだが、もうひとつの美術館は、県内外の公立美術館の学芸員や、類似の障害者のアートを扱う美術館(ボーダレス・アートミュージアムNO-MA、るんびにい美術館、鞆の津ミュージアムなど)との協働の実績やネットワークを持ち、まだ障害者の芸術活動が一般に知られていない時期から、全国各地の各種実践を見守りながら、互いに応援しあってきた存在である。この分野でのネットワークの質と量は抜きん出ている。TAM会議に参加する人たちが、意識するしないにかかわらず、もうひとつの美術館が培ってきた財産ともいえるネットワークに接続することができている点は、特筆すべきことである。
ワークショップはアーティストと出会う場所
取材に訪れた日、もうひとつの美術館では、彫刻家の黒田太郎さんがナビゲーターを務めるワークショップ「もうひとつのくらぶ」が行われていた。

もうひとつのくらぶの様子
梶原 いわゆる健常の人は自分で自分のやっている表現について伝えることができるけれど、知的などの障害のある人はなかなか伝えることができません。アーティストとして活躍している障害のある人は、偶然に才能を見出された人だったりします。こうしてワークショップをする中で、あらたな才能と出会いたい。また、別に専門家やプロにならなくても、さまざまな表現が人との関係から生まれることを伝えたいんです。
ワークショプでは、机に広げられたひとつの大きな紙に、参加者全員が好きな場所に思いおもいに絵を描いて、好きな形に切り取り、自分だけの絵をつくっていた。言葉で説明すると簡単だが、ひとつひとつの手法が、参加する一人ひとりの表現が伸び伸びと出てくるスペースを確保しながらも、その場に居合わせた人同士がコミニケーションを交わせる(したくなかったら、しなくてもまるで問題なくできる)ような工夫がされていた。
黒田さんも、参加していた障がいのある息子をサポートしていた館長の梶原さんも、アシスタントに入っていた友常みゆきさんも、さすがベテラン。所作も声掛けも全てがさりげなく、自然体で洗練されていることにびっくりさせられた。ワークショップに立ち会わせてもらったことで、美術館のコンセプト「みんながアーティスト、すべてはアート」を、身体ごと教えて(あるいは、ひたらせて)もらえたように感じた。
理念を言葉にして掲げているだけでは生み出すことのできない、実践の蓄積としての豊かさが、もうひとつの美術館の活動の中にはある。が、こうした豊かさというものは、得てして言葉にしづらいものだ。だからこそ、言葉を超えて理念を共有し、この場自体を守り、育てる人の輪がさらに広がっていくことを願う。
2025年12月
取材・文:友川 綾子

梶原 紀子
もうひとつの美術館 館長
八木一夫に影響を受け陶芸を学ぶため京都工芸繊維大学工芸学部無機材料工学科に入学。京都の町家に暮らし、寺院めぐりをするうち、建築空間に興味を広げて武蔵野美術大学造形学部建築学科に入学。卒業後はJAZZ喫茶でアルバイトをする傍、建築家 故毛綱毅曠の書籍制作に携わり、建築デザイン事務所に勤務した。1998年長男の小学校入学を機に栃木県那珂川町(旧馬頭町)に移住。二男の子持ち。次男が自閉症であることもこの活動のきっかけの一つ。
明治大正時代に建てられた廃校校舎をつかって、2001年よりハンディキャップのある人たちの作品を中心に、既成の枠にとらわれないアートを紹介する、もうひとつの美術館(Mob museum of alternative-art )を全国に先駆け開館。
全国公募入選作品展「なかがわまちアートフォーレスタ」を2008年2011年2014年と開催して、障がい者の芸術創作活動を支援し、まちづくりに繋げている。
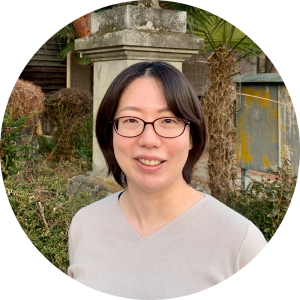
五味渕 仁美
とちぎアートサポートセンターTAM、もうひとつの美術館 スタッフ
栃木県出身。茨城大学教育学部情報文化課程アート文化コース卒。「もうひとつの美術館」での博物館実習をきっかけに障害のある人たちの表現の面白さと美術館の活動に惹かれ、卒業後地元に戻り、認定特定非営利活動法人もうひとつの美術館に入職、現在に至る。2017年からは「とちぎアートサポートセンターTAM」も兼務。

