「魂の表現」をすくい取り、育む環境を創造する。アール・ブリュット パートナーズ熊本(熊本県)

〜10年間で2万人が来場。「アール・ブリュット展覧会」が繋ぐネットワーク〜
フランスの画家ジャン・デュビュッフェが提唱し、作為のない個性や自発性に基づいた表現を称揚する「アール・ブリュット」の名を冠する展覧会「生(き)の芸術 アール・ブリュット展覧会」が、2024年12月に熊本県立美術館で第10回目を迎えた。障害者らの生み出す優れた作品に出会い、彼らの作品を原動力に、評価につながる仕組みやネットワークづくりに奔走してきた、展覧会事務局であり、熊本県の支援センター愛隣館を運営する三浦貴子さんと納富久さんにお話を伺った。
支援があれば、世に出る人がもっといる
お二人が所属する愛隣館は、熊本県山鹿市を拠点とする昭和25年創設の社会福祉法人愛隣園の障害者支援施設だ。生活支援事業に加えて、障害者芸術文化活動支援センター事業も行う。現在は、年に一度開催する展覧会をメインに据えながら、相談支援対応、作家・作品の調査発掘、研修会の開催、移動美術館、地域活動支援センター内でのギャラリー運営などを展開する。三浦さん、納富さんは社会福祉法人の事業もこなしつつ、他のスタッフとも連携して運営を行っている。
愛隣館が支援センター事業を受託したのは2017年からだが、その活動基盤と豊富なネットワークは、三浦さんが企画し2014年に設立された市民団体に負うところが大きい。
三浦 この展覧会を主催する「アール・ブリュット パートナーズ熊本」は、障害のある人々らの芸術活動を推進する目的で、市民団体として結成し、愛隣館が事務局を担っています。
「ら」と一文字入れているのは、障害者手帳を持たずとも、ご高齢の方も含め様々な支援を必要とされる方、生きづらさを抱える方がいらっしゃり、その方々も取りこぼさないようにするためです。
芸術活動支援のきっかけは、愛隣館の近くに住む作家、松本寛庸さんとの出会いだった。彼の画は2010年にフランスで開かれた「アール・ブリュット ジャポネ展」にも選出されており、同展が熊本に巡回するところだった。
三浦 松本さんと彼の作品との出会いで、「支援があれば、社会に認められる人々がもっとたくさん居る」と考えたのです。まずは熊本に巡回してくる同展や障害のある方の作品について、福祉に関わる方やご家族などの支援者をはじめ多くの方に浸透させることが大事だと、県内で障害福祉に造詣の深い方や、支援・応援くださる方にお声がけして、80名ほどで応援する会を組織しました。

松本さんの絵画作品
感動と共感が人を動かす。県内全域をカバーする幅広いネットワーク
応援の会結成1か月後、2014年の1月には、「アール・ブリュット パートナーズ熊本」が発足。結成当初から現在まで継続している役員やアドバイザーが多く、リストには福祉団体、行政、協議会、新聞社、美術系の有識者の名前が並ぶ。これだけ幅広い人を巻き込む背景には、三浦さんが熊本市や福祉団体協議会等で執務経験を持つことも一役買っているが、一番大きいのは作品の持つ力だという。
三浦 セクター化しては広がらないので、アクセスが均等になるよう県社協などを通して全体にお声がけするなど気を付けています。でも、みなさんオープンマインドで、作品に対してこれはいい、素晴らしいと感動して、共感で繋がっていったんですね。
当初一番連携についてのハードルと感じていたのは文化セクターでした。美術館って敷居の高いイメージで、恐る恐る作品を持って行きました。他の役員の方も、直接作品を持って色々な方に見せに行っていたみたいです(笑)組織より人とつながることが大事。共生社会の実現を目指すという大きな意義もありますから、想いを共有できる方と出会えるかどうかですね。出会った学芸員の方には、「20ヶ所くらいに持って行って展示したらたくさんの人に伝わりますよ」と言われて。20はさすがに多いなと思って少し減らしましたけど、まずは知り合いのところから、“移動美術館”として展示をはじめました。
減らしたとはいえ、納富さんの頑張りにより、最初の年から県内16ヶ所、翌年も15ヶ所で“移動美術館”を開催したというから驚きだ。初年度はそれに加え、山鹿市の国指定重要文化財の芝居小屋・八千代座を会場に「一日美術館」と題して作家7名の作品を展示し、福祉・美術両分野の専門家による研修会も開催。翌年からは1週間前後の展覧会が始まり、3回目の開催からは熊本県立美術館の本館で2週間ほどの展覧会という現在の形にまで発展した。その一方で、移動美術館も継続している。
三浦 最初はまったく予算がなく、市民団体の会長と事務局の私たちが寄付してやっと展覧会を行える状況でした。助成金や支援センターの運営などでようやく基盤が出来ていって、当初目指していた美術館との共催や、美術館主催の企画展に障害のある作家達が招へいされるという夢(熊本市現代美術館主催の企画展「ライフ」「ライフ2」に登録作家達が選出)も着実に叶っています。

移動美術館の様子
人々の交わりが浮かび上がる、10回目のアール・ブリュット展
10回目となるアール・ブリュット展覧会に参加した県内在住作家は、8歳から79歳まで28名。展覧会の開始当初から一貫して、作家や作品は美術のキュレーターが選出する。
三浦 作品の評価は美術の専門家にしていただくことが重要と考えていて、今回担当のつなぎ美術館 学芸員の楠本智郎さんはキュレーターとして四代目になります。私たち素人からすると「えっ」というものが選ばれることもあり、専門家が価値を見出す目はすごいなと思います。

平面の絵画に限らず、様々な作品が出展されている
楠本さんは、審査過程で作家や支援者と出会い、背景やストーリーを理解していくなかで、「作品の最終的なアウトプットだけでなく、そこに到達するためのプロセスやそのプロセスに人が共感することが、アール・ブリュットに限らずアート全般で大切だと再認識した」と言う。来場者がアール・ブリュットの裾野の広さ、誰でも表現者でありうるという可能性を感じ取れるよう、表現方法のバリエーションなども加味して作品を選出した。
納富 10回フル出場の作家さんもいますが、キュレーターの方によって選出される作家は変化します。キュレーターが交代していくのは、みなさんの作品にさまざまな角度から光を当てることができる、という意味で重要ですね。
展覧会場は、人々の交流の場にもなっている。会場には実演スペースが設けられ、日課のように作家が来場し、作品制作を行う様子も間近で見られる。販売コーナーには、全県下から障害のある人の表現から生み出されたプロダクトが集められ、販売は熊本市内にショップを運営するチームが担う。展覧会場の受付には、作品を観てほしいという当事者や家族、障害者の芸術文化活動に関わる仕事がしたいという学生なども訪れ、相談窓口と化することも。また今回は、韓国の団体との出会いから、4名の韓国作家の作品展示も行い、開会式には家族ぐるみで来日した作家たちの姿も見られた。

展覧会の実演スペースにもたくさんの観客が
これまで10年間の展覧会で約2万人が来場し、回収したアンケート総数は3,400枚にのぼる。展覧会パンフレットに掲載するために、専門家にAI解析を依頼したというアンケートからは、作品が来場者に感動をもたらし、作家がその作品や制作活動を通じて地域社会に活力を与えていることが示された。
展覧会場の最後を締めくくるのは、家族や施設職員等、支援者からのメッセージだ。「彼らの存在が、この芸術活動にはすごく大きい。それをぜひ伝えましょう」と楠本さんが発案した。「息子が一年で一番輝く2週間だ」など、寄せられた声から、この展覧会が彼らを大いに勇気づけ、喜びをもたらしていることが伝わってくる。
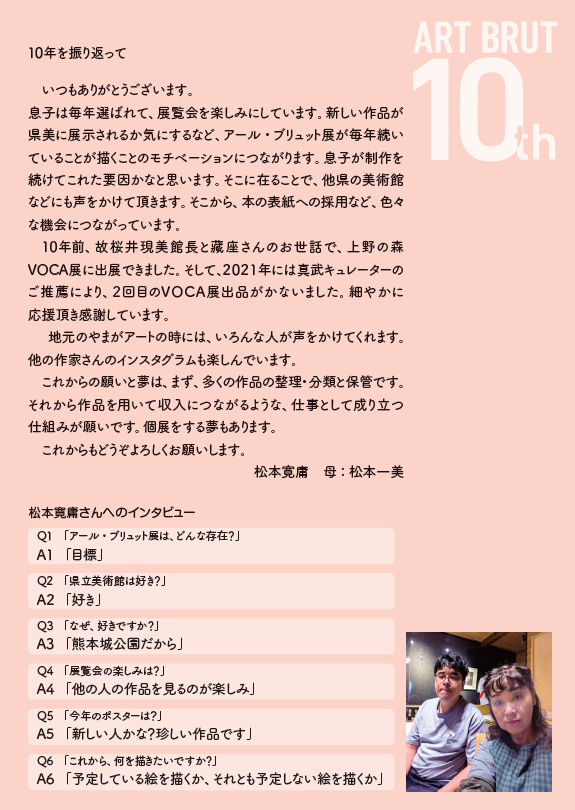
展覧会によせられたメッセージ
支援は常に1対1。家族や支援者との向き合い方
たった一人の支援から始まり、現在の登録作家は125名にのぼる。どのように作家発掘を行っているのだろうか。
三浦 最初のころは、応援会などの関係者から情報提供いただくこともありました。ウェブサイトを整備した時にGoogleフォームで作家登録システムを作り、今年の参加者には自らエントリーした方も。一番役立っているのは、毎年展覧会場で実施しているアンケートです。シンプルな構成で、自由記述の感想欄と、「紹介したい創作活動をしている障害のある知り合い」の回答欄のみ。身近に思い当たる方がいると、どうもみなさん紹介したくなるようです。
事務局と支援者との距離が近いことも特徴だ。展覧会開催時に限らず、いつでも相談や連絡が来るという。
三浦 1対1の人間関係が登録作家の数だけあるという状態です。作家は家族だと思っています。熊本地震のときは作家全員、みなさんの家に電話して安否確認をしました。作家とご家族と一緒に美術館に行ってお茶をしたり、旅行にも行ったことがあるんです。あるとき、船に乗って、猫が有名な島を訪ねたのですが、「普段気を使って遠出できなかったので、初めての旅行だ」と喜ぶご家族も居られて。旅先での体験を作品化した作家さんもいらっしゃるんですよ。

荒木聖徳さんが旅の体験をもとに制作したちぎり絵作品
また、2022年の展覧会では、支援者に焦点をあてたワークショップも企画された。紙をハサミで繊細に切り込む作家、藤岡祐機さんの作品を、お母さまと参加者が一緒に壁一面に展示していった。三浦さんは「やはりご家族が一番近くにいて、お母さまが表現を発見することが多いです」という。

藤岡さんの作品を使ったワークショップの様子
今回の展示では、28名の参加作家のうち半数以上が、事業所等の支援なく芸術活動を行っている。必要があれば、芸術文化活動に関することだけでなく、生活支援にも繋ぐ。最近は作品の保管の問題や販売の相談などもあるそうだ。
三浦 これまで、相談を断ったことはありません。一人暮らしで生活保護を受けている方に「個展をするから手伝ってもらえませんか」と言われたら、断れませんね。在宅で創作活動している方はたくさんいらっしゃいますし、つなぐ人が居なくて埋もれている方も多いと思います。相談者が増えていった場合、パーソナルニーズにどこまで応えられるか、課題感もあります。今は私たちの他に相談できる機関がない状態ですから、できるだけ受けていきたいです。
発信力の強化。継続への原動力
10周年にあたって、展示作家を網羅した記念冊子を作成した。これまでのあゆみや、歴代のキュレーターによるコラム、アンケート分析なども掲載されている。この監修や校正に加え、掲載されている作家のポートレートを撮影しているのは、市民団体の結成当初からアドバイザーとして関わり続ける熊本日日新聞の岩下勉さんだ。ほぼ全員の自宅や作業場を訪ね、「全員のライフストーリーが頭に入っている」と言う。
また、近年は動画での発信にも力を入れており、ホームページには開会式やギャラリーツアー、参加作家全員の制作動画が並ぶ。
納富 以前、展覧会の当日に会場に来る途中でお亡くなりになった方もいらっしゃるんです。会場に来られない作家も展示の様子を動画で体感できるように、独学で動画制作を始めました。制作風景の動画はご家族や施設の方にも協力いただいて1分以内で構成して、展覧会場で上映したり、Youtubeで発信したりしています。ハサミで繊細な切り絵を作る渡邊義紘さんのお母様から「息子は、全部ハサミで、いっきに作品を切ります。作品だけ見た人に、カッターで作っていると思われたら悔しい」というお話を聞いて、昨品を作るプロセスにも驚きがあることを共有できればと考えました。
制作風景ビデオは全作家分、1分程度でまとめられている
これまでは美術分野に注力してきたが、舞台芸術分野にも繋がりが生まれている。
納富 昨年度、熊本県立劇場のイベントで障害のある方の参加者募集に協力したことをきっかけに、今年度から劇場の評価委員を務めることになりました。社会包摂事業に関して福祉分野の知見からフィードバックを行っています。今はまだ手が回らないですが、我々の強みであるネットワークや劇場が持つ知見も活かして、一緒に熊本を盛り上げていけたらいいなと思います。
大規模な展覧会を毎年行うには人的、資金的に難しさもあるが、それでも展覧会を続けていく、強い思いが三浦さんにはある。
三浦 今ではこの展覧会が作家さんや作品を育む支援者たちの人生の一部になっていて、それが私たちにとっても続ける原動力になっています。障害のある人の表現がアートとして認められるということが、障害特性と呼ばれるもののもつ力や独自性を伝え、社会を変える一助になると信じています。
2024年12月
文:橋爪 亜衣子

三浦 貴子
アール・ブリュット パートナーズ熊本 事務局長
障害者芸術文化活動支援センター@熊本 愛隣館 センター長
2012年 ~ 2023年 内閣府障害者政策委員会 委員長代理
2023年 ~ 全国身体障害者施設協議会 副会長
2023年 ~ 九州障害者支援施設協議会 会長
熊本県山鹿市在住。障害者支援施設愛隣館総合施設長。
山鹿市在住の障害のある作家の支援をきっかけに、芸術活動支援を通した地域
共生社会の実現を目指す。熊本県内の芸術活動支援市民団体「アール・ブリュ
ット パートナーズ熊本」発起人。

納富 久
アール・ブリュット パートナーズ熊本 事務局次長
障害者芸術文化活動支援センター@熊本 愛隣館 センター次長
熊本県山鹿市在住。障害者支援施設愛隣館サブチーフ。
2014年、熊本県内の障害のある人々らの芸術活動支援市民団体「アール・ブリュット パートナーズ熊本」、2017年「障害者芸術文化活動支援センター@熊本 愛隣館」発足時より事務局を務める。2024年より、熊本県立劇場文化事業評価委員。

